「洋紙と用紙」第32回「日本の洋紙―黎明期」その2
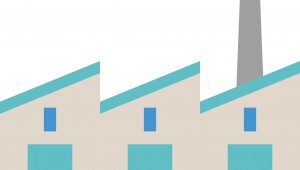 (前回の続き)
(前回の続き)
日本製洋紙のはじまり
輸入紙に対抗するには、国家として自給自足ができねばなりません。そこで、機械を輸入し、外国人技師を高給で招き、和製洋紙の製造に取り組みました。苦労の末、日本に最初の洋紙を誕生させることができたのは、明治7年(1874年)のことになります。
当時の模様を、いくつかの項目に分けて記録をたどってみます。
メーカー
先駆者は有恒社で明治7年に創業。明治8年には蓬萊社製紙部、三田製紙所、抄紙会社(後の王子製紙)が操業し、同9年のパピール・ファブリック、少しあいて12年には神戸製紙所(後の三菱製紙)が操業し、この6社が日本の洋紙の創成期を築きます。
抄紙機
有恒社がイギリス製60インチ長網、蓬莢社―イギリス製60インチ長網、三田製紙所―アメリカ製57インチ円網、抄紙会社―イギリス製78インチ長網、パピール・ファブリック―ドイツ製1・52メートル長網、神戸製紙所―アメリカ製72インチ円網。
以上が、操業を開始したときの設備内容です。ここから、日本の洋紙が生まれました。
設備はできても、当時の日本には抄紙技師も、手伝える職人もいませんでした。そこで各製紙会社は外国人技師を高給で雇い、建設、設備、そして抄紙技術を教わりながら操業にあたりました。
原料
まだ木材パルプが発明される前であり、原料には破布つまり木綿ボロを使いました。破布を集荷・選別し、苛性ソーダで蒸煮、さらに漂白してパルプとしています。しかし、破布もたくさんあるわけではなく、集荷には主要な人口密集地に手をまわすなど、それ自体苦労をともないました。また、外国も同様だったようです。
わらパルプは明治15年に、サルファイト・パルプは明治22年、グラウンド・ウッド・パルプ(砕木パルプ=GP)は明治23年にそれぞれ開発されますが、それはまだ後のことになります。
ここで、各パルプのことについてちょっとふれてみますと、欧米ではわらパルプの原料に麦わらを仕様。日本では麦より稲が多くとれる条件を生かし、稲わらのパルプ化を独自に開発。明治15年には木綿ボロ4に対しわらパルプ6の割合で抄造しています。
このわらパルプの開発は、洋紙製造にとって革命的な出来事でした。原料確保問題の解決、品質向上、量産化などたくさんのメリットをもたらしました。これをさらに大きく変えたのが、木材パルプの開発になります。
初期の洋紙
当時の和製洋紙の種類には、筆記用紙、上等印刷用紙、新聞用紙、色紙、吸取紙などがありました。しかし、品質的には輸入紙にくらべて大分劣っていたため、需要先をつくり、販売にこぎつけること自体難しく、日本国内で市民権を得るにはまだたくさんの苦労、改革を必要としました。
それは、日本には昔から親しまれている和紙があり、量的にも和紙だけで間に合っている状態もあったからです。特に、和紙は植物繊維を使った独特の紙として、当時でも世界のトップレベルにあったので、できたてで不安定な機械抄きの紙はまさに紙の異端児のようでもありました。
和製洋紙にやっと陽光がそそいだのは、地券紙の登場からになります。
明治9年、同6年に公布された地租改正事業に関連し、政府は三田製紙所を通して「地券判」という印刷用紙を注文しました。その量が莫大な量であったため、三田製紙所は各製紙所に抄造を依頼し、納品しています。
この紙は、全国の土地所有者に地券を交付するためのものでした。この地券証用紙を当時は地券判(やがて地券紙と呼ばれる)と呼んでいます。寸法は1尺9寸5分の2尺5寸で抄き、4截の9寸7分5厘の1尺2寸5分にして使いました。厚手で抄きやすかったので生産も上がったそうです。明治9年から13年にかけて大量に抄造されましたから、当時販路不足に悩んでいた各製紙会社にとって、地券紙は救いの神でもありました。また、明治10年の西南戦争を契機とした新聞・雑誌への関心の急速な高まりは、発行部数を増やし、洋紙需要を増大させています。このことは、創業以来苦境にあった製紙業の経営内容を大きく改善させることとなりました。
(続く)